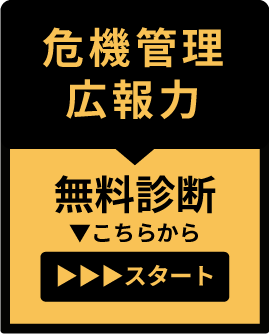危機管理広報
不祥事や品質問題、事故など、予想もつなかないタイミングで発生するクライシスに対して、
経営・ビジネス上必要とされる広報対応をワンストップで提供

リスク・クライシスに迅速に対応するため、危機管理広報のサポートを定額プラン方式で提供
危機時において適切かつスピーディに初動対応・広報対応を進めていくために危機管理広報のスペシャリストによる広報対応支援サービスとして2つの定額プランをご用意しています。
こんなお客様に
- いつ発生するかわからないリスクに備えたい
- メディア対応時のセカンドオピニオンとして外部の専門家のアドバイスが欲しい
危機管理広報サポートプラン
(定額制のサブスクリプションモデル)
サービス内容
発生したリスク事案に対して電話やメールでのアドバイス(対応方針・想定Q&A・公式見解・リリースなどへの助言)
※土日祝日も対応可能
- クライシスが発生した際に外部の専門家のサポートが必要
クライシス初動対応サポートプラン
(案件ベースのスポット対応サービス)
サービス内容
- 発生した事案の危機レベル判断(記者会見の要否・タイミングなど)
- 初動対応のコンサルティング(事案内容、社会トレンドなどをふまえた対応方針案の策定)
- いずれもWeb会議ツールを使用してオンラインによるご相談が可能です。
- 想定Q&A・公式見解・リリースなどで弊社スタッフが文書などを作成する場合、および「メディアトレーニング」「記者会見の運営サポート」などは別途タイムチャージ制です。
危機管理広報活動フロー&ソリューション
-
Step01
事前準備 /リスクマネジメント
- 自社リスクの洗い出し
- 社員への啓発教育による危機発生の回避
-
Step02
クライシス発生時の対応
- クライシス発生時の初動対応
- ダメージを軽減する広報対応
-
Step03
リカバリー
- 安心安全に関する情報発信
- 負のイメージを好転させる情報発信

事前準備 /リスクマネジメント
お困りごと
- 社員が普段から取材に勝手に答えてしまっているがどうしたらよいか
- 自社にどのような広報上のリスクがあるのか知りたい
- 「危機管理広報」を行いたいが、何から始めたらよいか
-
ソリューション
メディアセミナー (初動対応、メディア対応話法)/メディアトレー二ング
クライシス発生時のメディア取材対応力を強化する実践的なプログラムを「メディア視点」と「企業広報視点」の両面からご提供します。
オズマピーアールが提供する取材対応トレー二ングメニューはこちら -
ソリューション
危機発生時の対応方針準備ワークショップ
危機発生で緊急記者会見や取材対応を行う際には、情報発信を見据えた方針を組織内部で検討・決定しておくことが重要です。方針決定のための会議運営と報道資料作成のプロセスを体験する実践型講習を提供します。
-
ソリューション
危機管理広報マニュアル制作
クライシスに全社的に対応するため、万一の際の行動基準やルールをマニュアルで整理し、「属人的な対応」から「組織的な対応へ」と強化します。
-
ソリューション
報道論調分析
新聞・TV・雑誌・ニュースサイトでの報道傾向を分析し、図やグラフを用いたレポートで可視化。コミュニケーションプランの軌道修正と、ダメージ・コントロール施策に活用します。
-
ソリューション
SNS分析(ソーシャルリスニング)
Twitterやブログ、大型掲示板などソーシャルメディア上の生活者の書き込みやつぶやきをソーシャルリスニングツールを活用して解析。ソーシャルメディア上にある生活者情報の定量・定性分析からネット世論の動向を把握します。
-
ソリューション
危機管理広報eラーニング講座
クライシス発生時には、現場から的確に第一報を上げられるように組織内部で意識づけと基礎的な知識の共有をしておくことが重要です。現場の社員・職員が最低限知っておくべき知識や行動を手軽に学んでいただけるクイズ形式のeラーニング講座を提供します。

クライシス発生時の対応
お困りごと
- クライシスが発生したとき、広報は何をすればよいか、何から始めればよいか知りたい
- クライシスが発生したとき、すぐにサポートをお願いしたい
-
ソリューション
クライシス対応コンサルティング/広報資料の作成サポート
クライシス発生後の対応によっては、ダメージを軽減したり、ポジティブなイメージへ転換することも可能です。リスク・クライシスの現場経験豊富なスタッフが、事態を速やかに収束するべく、サポートします。
-
ソリューション
クライシス発生時の記者会見開催サポート
新聞・テレビなどへの会見案内方法から会見会場の手配、当日対応、報道モニターまで、広報実務的な業務を迅速にサポートします。
-
ソリューション
ネットリスク対応コンサルティング/ネットリスク版 危機管理広報マニュアル
企業の対応や姿勢について、不満や不信感が⽣じた際、ソーシャルメディア(SNS)などに否定的な書き込みや投稿などを⾏うことで、瞬く間に情報が拡散して「炎上」する場合があります。ブランド毀損や企業の事業継続を脅かす事態にまで至らないよう、炎上発生時の初動対応アドバイスや事前の対応マニュアル作成を通じて、事態の収束に向けたコミュニケーションをサポートします。

リカバリー
お困りごと
- クライシス対応の終了後はどのように広報活動を行っていけばよいか
- そろそろ販促活動を再開させたいが問題ないか
- リスクで傷ついたブランドイメージを回復させたい
-
ソリューション
報道論調分析
新聞・TV・雑誌・ニュースサイトでの報道傾向を分析し、図やグラフを用いたレポートで可視化。コミュニケーションプランの軌道修正と、ダメージ・コントロール施策に活用します。
-
ソリューション
リカバリー広報
信頼回復までのロードマップを「不安払拭期」「信頼回復期」「信頼強化期」の3フェーズに分けて戦略的に対応・サポートします。
-
ソリューション
SNS分析(ソーシャルリスニング)
Twitterやブログ、大型掲示板などソーシャルメディア上の生活者の書き込みやつぶやきをソーシャルリスニングツールを活用して解析。ソーシャルメディア上にある生活者情報の定量・定性分析からネット世論の動向を把握します。

メディア出身者や企業広報プロが
最適な施策を提供
メディア出身者の知見、IR分野の視点も含めた企業広報プロの専門知識、省庁・大手企業やベンチャーなど幅広い業種での実績がわれわれの強みです。 クライシスへの備えから緊急時対応、事後のリカバリーまで、ワンストップで最適なコミュニケーション施策を提供します。
実績
官公庁、公的機関及び企業において、年間100件近いセミナーやトレーニング、危機管理広報コンサルティングを手がける当社は、 メディア出身者により豊富な知見と企業広報のプロによる手厚いサポートが最大の強みです。
危機管理広報・有事対応事例
- 飛行機・道路関連などの交通インフラ領域の事件・事故対応
- 食中毒事件、異物混入事故などの食の安全対応
- 医薬品の欠品問題、化粧品品質不良問題などのヘルスケア領域の危機対応
- 個人情報流出、セクハラ事件、怪文書騒動などの一般リスク対応
- 特殊ジャーナリズムや市民運動などが企業に与える影響のデプス調査
- 経営陣内紛・特許訴訟などの経営リスクコンサル
- ネット上のうわさ拡散・風評被害対策などのネットリスクコンサル
メディアトレーニング・セミナー事例
- 中央官庁の報道官・管理職
- 航空会社、高速道路会社、IT企業などの社長・役員
- 食品・飲料・製薬・自動車メーカーなどの社長・役員・管理職
- 商業施設、テーマパークの役員、国立大学の学長、理事 ほか