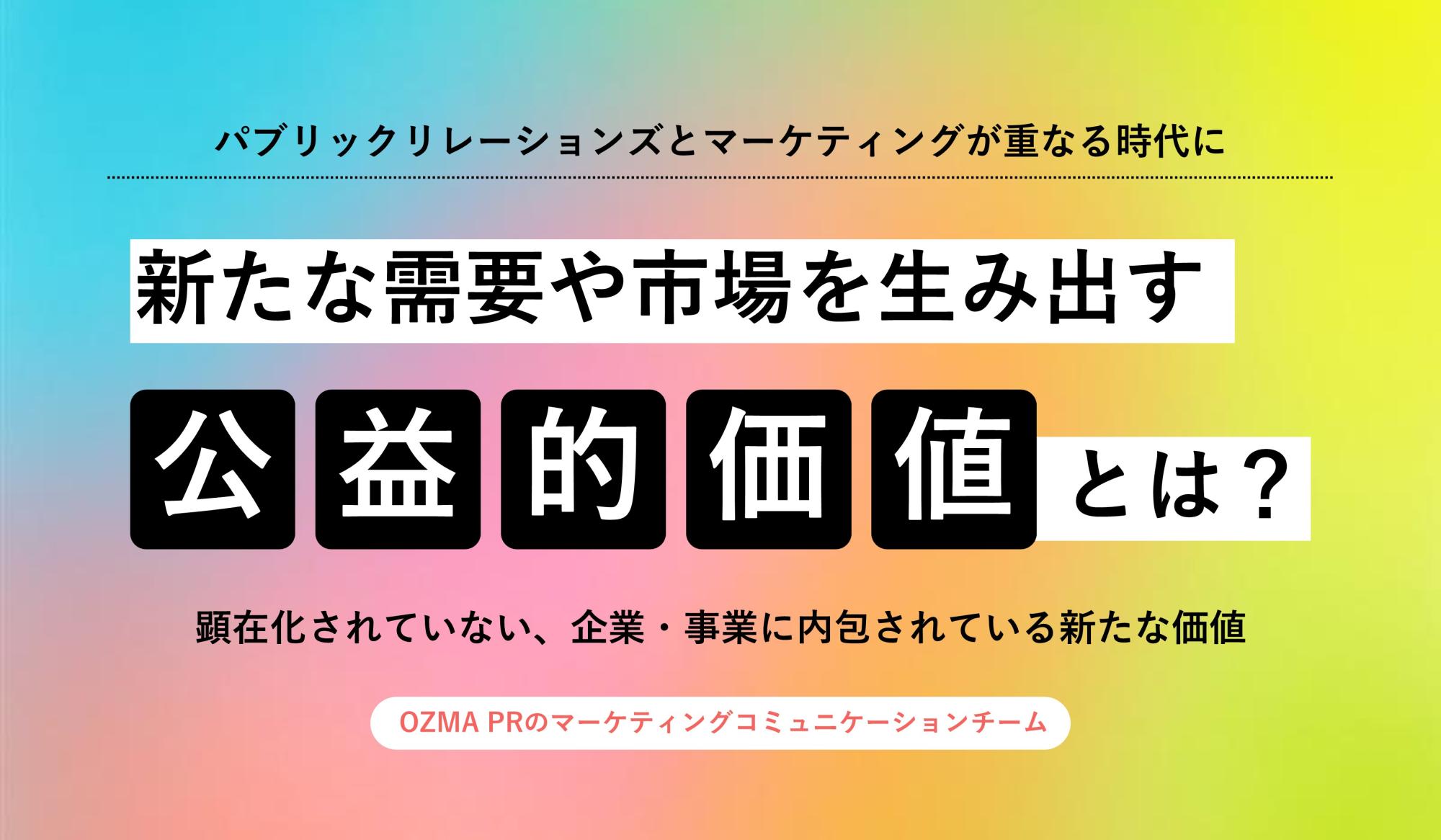PRの明日を考える:Advertising Week Asia 2024で見えた潮流
2024年9月17日(火)~20日(金)の4日間、東京アメリカンクラブで開催された「Advertising Week Asia 2024」に参加してきました。
このイベントは、2016年に初回開催され今年で第9回目を迎えるアジア最大級のマーケティング&コミュニケーションイベントです。「熱狂を作り出す~Creativity excites industries」をテーマに広告業界のみならず、あらゆる業界から最新の知見を集約して開催されています。

2024年は、
・生成AIの台頭を受けて変わる創造性のあり方
・目まぐるしく変わるコミュニケーションチャネルの活用方法
・社会課題に対して求められる視点
などPRパーソンとして関心を持たずにはいられないテーマが多く議論されるほか、当社代表取締役社長の中尾敏弘もパブリシティをテーマにしたセッションに登壇するということで、マーケティングコミュニケーション部のメンバーが参加してまいりました。
中尾のセッションでは、パブリシティは販売促進や企業ブランディングの目的達成のためのコミュニケーション活動の一つであり、昨今の生活者環境や意識を鑑みると販促やブランディングにおけるPRの役割が高まっていると解説しました。
※詳しくはこちらをご覧ください。https://ozma.co.jp/news/detail/186

今回はPRをはじめ、マーケティング&コミュニケーション業界のトレンドに触れた当日の様子や感想をレポートしたいと思います。


■3つのテーマから考える、マーケティング&コミュニケーション業界のトレンドとPRのこれから
60個以上あるセッションの中でも、今回参加したメンバーが特に興味を持ったテーマは大きく以下の3つ。
① 生活者インサイトの探り方の移り変わり
② 既存のメディアと新しいチャネルのこれからの活用方法
③ データやAIを用いた広告配信と効果測定
様々なセッションに参加する中で感じたことを、各テーマに沿ってご紹介します。

① 生活者インサイトの探り方の移り変わり
生活者とのコミュニケーションを考えるうえで欠かせないのが生活者インサイトを探ること。マーケティングにもPRにも欠かせない生活者インサイトですが、その情報収集の方法は変わりつつあります。
今までのマーケティングでは、消費者の購買行動における情報収集経路として「AISAS」(認知⇒興味⇒検索⇒購買⇒シェア)を用いることが多かったのですが、最近はさらに、SNSを中心として、「SEESAS」(目的なく見る⇒出会う⇒好感認知⇒検索⇒購買⇒共有)に変容しつつある、といった内容のセッションもありました。
またその他に、外資系PR会社出身のマーケッターが、本当の意味で「生活者本位」なブランドとはどの様なブランドなのか?を、インサイトをとらえながら、深堀りすることを重視していました。
事業側が売りたいものと伝えたいことのギャップや、購入者と実際のユーザーとのギャップなど様々なインサイトギャップについて着目する必要があるという内容は、PRパーソンとしても共感する部分が多かったです。インサイトの探索はPR業界が得意とする領域でもあるため、今後はさらに的確に消費者の行動変容を促せるように購買行動の分析などを重ねていく必要がありそうです。
② 既存のメディアと新しいチャネルのこれからの活用方法
生活者に情報を届ける際、どんなメディアでどんな情報を発信するかはもっともPRの手腕が問われる分野といえます。そんなメディアに関するテーマをメディア運営者やPRの第一人者の方々が議論されていました。

例えば、昨今、視聴率の低下が取りざたされるTVは、新たにコネクテッドTVなどを活用しながらその価値を高めています。
例えばある民放公式テレビ配信サービスはあらゆる視聴データをきちんと確保して進歩していくことで、社会インフラになることを目指しており、将来的には、見逃した番組を見る能動的なツールから、「情報を求めていてもいなくても取りあえずそのサービスを開いてみる」といった受動的なツールに遷移していくことを理想にしています。セッションを聞いて、新しいメディアの当たり前としての立ち位置を確立しようとしているのだと感じました。
現在はあらゆるモノやヒトがメディアになり、その盛衰が激しさを増しているため、新しいチャネルの可能性を絶えず探ることは、PRでも必要不可欠になっています。また、PR起点で新たなメディアを生み出すことができたらより業界が活性化しそうだと思いました。生活者が必ず目にする場所やタイミングを探り、その可能性を模索することもできそうな気がします。すでに、テキストと画像のみのプレスリリースを映像化したビデオリリースも登場している例があり、PRとメディアがさらにタッグを組むとどうなるのか考えてみたくなるテーマのセッションでした。
③ データやAIを用いた広告配信と効果測定
23年に施行されたステマ規制法による情報の信頼性や、サードパーティCookieの規制/廃止による生活者のプライバシー保護など、インターネットやSNSが当たり前になったからこそデジタル広告・SNSマーケティングに問われるモラルや課題が増えています。企業やメディアは今後よりいっそう、信頼性を担保しながら的確に情報を届ける手法を探していかなければなりません。そんなテーマに焦点を当てたセミナーやサービスの紹介も多く見られました。
まず、ターゲティングにはAIの活用が不可欠な印象を受けました。というのも、海外のDOOHでAIとビッグデータを組み合わせることで、パーソナライズされた広告表示やリアルタイム表示を実現したり、従来のインストリーム広告ではなく記事や動画の特長に合わせた広告をAI動画解析によって人間が最も閲覧する場所に配信したりと、AIを活用した広告サービスが増えていたからです。(セッションも多くの参加者で賑わっていました)
一方、PR業界ではまだまだAIをを活用できる余地が大きいのではないかと思います。広告ではないコミュニケーション施策にとって主流になるAIの活用方法とは何か、試行錯誤を続けていく必要があるなと感じました。
また、AIやデータサイエンスは広告やPRの効果測定にも影響を与えています。例えば、これまで効果が可視化されづらかったTVや紙媒体においても、広告換算に替わるモノサシを作るために、データサイエンスのプロフェッショナル企業が、視聴率では説明がつかない効果解明を試みている事例がありました。視聴率・GRPによりかからなくてもクリエイティブの評価軸を抽出できるので、画期的な取り組みとなりますし、もしCMなどにこれが適用されるようになれば、緻密に評価されてしまうので、クリエイターにとってはシビアな時代が到来しそうです。
このように、従来の効果測定で用いてきた「広告換算額」や「リーチ数」ではなく、社会への影響力や公共的価値を図る方法が模索されつつありますが、中長期的な効果を図るには変動要素が大きく、まだまだトライアンドエラーが必要になりそうです。また、データサイエンスの領域とも協力し、業界を超えて模索することでより正確な効果測定ができるようになるのではないかと感じました。