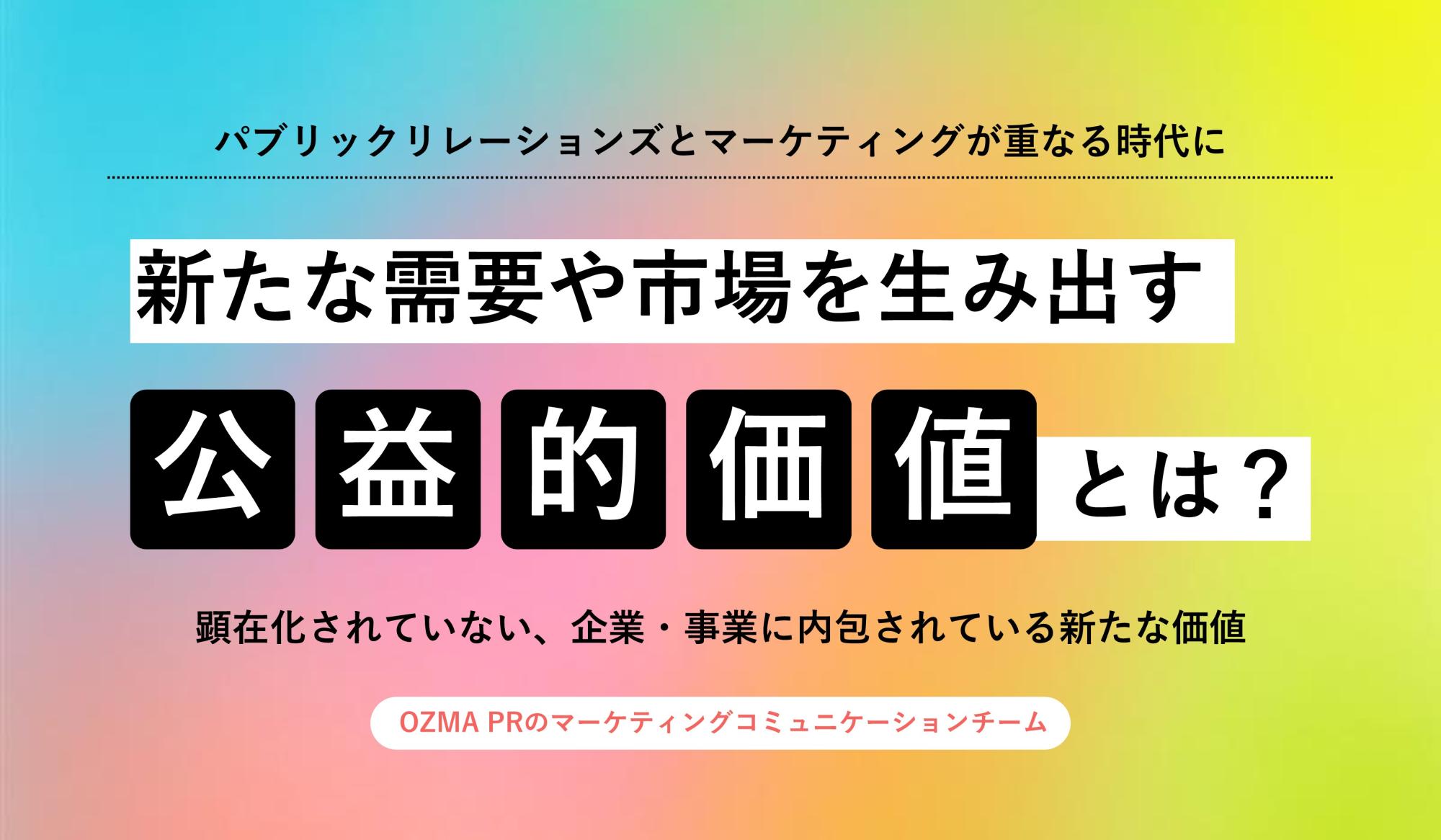PAリレー対談~ルール形成の現場から(5)公益の視点をもって進める、パブリックアフェアーズのポイント【後編】髙橋彰さん(ハイランダーパブリックアフェアーズ代表)
オズマピーアールは2020年6月より、多摩大学ルール形成戦略研究所と業務提携し、ルール形成市場のさらなる拡大と深化に向けて活動を進めています。社会構造の変容が急激に進み、それに伴うルール形成があらゆる分野で課題となっている今、新たな市場を作るためのパブリックアフェアーズへの関心はますます高まっています。
第5回は、公共政策コンサルタントの髙橋彰さんをお迎えしました。民間企業がパブリックアフェアーズに取り組む際に必要な視点についてお話をうかがった前編に続き、後編では、パブリックアフェアーズを実践するにあたっての設計や手法について、弊社井上とともにさらに紐解いていきます。
聞き手:井上優介(オズマピーアール パブリック・アフェアーズチーム)
(以下、本文)
パブリックアフェアーズで注意すべきポイント① 役所のキャラクターを理解する
井上:前編ではパブリックアフェアーズのあるべき姿についてうかがいました。後編ではより実践にフォーカスを当ててうかがっていきたいと思います。
パブリックアフェアーズの進め方や手法の面でポイントにすべきなのはどんなことですか。
髙橋:私はよく「役所のキャラクターを理解する」という言い方をしているのですが、官庁にもそれぞれの役割や担当領域によって特色があります。相談しに行く際にも、その点を考慮するかどうかで成否が変わるんですよ。
例えばヘルスケア領域でキャンペーンを展開したい案件があるとします。ヘルスケアといってまず思い浮かぶのは厚生労働省だとは思うのですが、最初の相談先として適切かどうかはよく考える必要があります。厚生労働省は健康増進や啓発活動もしているものの、本来は薬や食品など体に入るものの安全性を守る規制官庁です。広く生活者に働きかけるキャンペーンとなると、もちろん厚生労働省の中に得意なメンバーもいるのですが、むしろ経済産業省のヘルスケア部門に働きかけたほうが良いかもしれません。
一方で、キャンペーンの企画がどんどん進んで展開が広がっていくと、どこかの時点で規制に引っかかる可能性が出てきます。その際には安全性の担保といった議論が必要になるので、厚生労働省や、案件によっては消費者庁などの規制官庁ともコンタクトをとっておく必要が出てきます。
井上:各官庁の関係性や得意分野を見極めながら段取りを組んで進めていかなければならないんですね。こういうところこそ、官庁の目利きができる髙橋さんの力をお借りしたい場面です。

パブリックアフェアーズで注意すべきポイント② 情報収集・分析で重要なヒューミントとオシント
髙橋:もう一つポイントになるのは、情報収集や分析の手法です。パブリックアフェアーズやガバメントリレーションズにおいては、一般的には得られない情報が特別なルートで得られるものだと考えている人も少なくありません。実際、それを商材にしている企業もあると聞きます。しかしそういったいわゆる“普通は得られない話”には、注意点が二つあります。
一つは大前提として、公務員の守秘義務に違反している可能性があるので、その「教唆(そそのかし行為)」となるような要求はしてはならないという点です。最悪の場合、委託元企業まで責任が及ぶ可能性もあります。
もう一つは、こちらの方がより大事かもしれませんが、その話が果たして情報として正しいのかどうかは、プロの視点で見極める必要があるということです。
情報収集活動においては、人と直接接触することで得られる情報をヒューミント(英HUMINT:human intelligence)といいます。ヒューミントは非常に大事なのですが、他のさまざまな要素と合わせて分析する能力を持ち合わせていないと、扱いが危険な情報です。
井上:そうですね。私たちもヒューミントの収集を提案することはありますが、やはりオシント(OSINT:Open-Source Intelligence)と組み合わせて裏取りをきちんとすることも併せて行います。
髙橋:その通りです。ヒューミントだけで重要な情報が手に入ったと喜ぶのはいわば素人考えで、プロはオシントで情報を補足したり、あくまで総合的な分析の補助資料として扱います。ヒューミントとオシントを合わせて考えるとこうなっているであろう、というシナリオをつくって分析できるかどうかが問われるんです。
私が井上さんと仕事するうえでは、そういった過去のデータや国際比較など、多面的にオシントを考え合わせて、ヒューミントを評価できるデータづくりを一緒につくっていくようにしています。
井上:ここは呼吸を合わせるようにしていますよね。
昭和の陳情スタイルからは脱却して公正なコミュニケーションを
井上:日本のパブリックアフェアーズは米国などに比べるとまだ未成熟な部分もあり、今は過渡期でもあります。企業側の意識もアップデートしていくことが求められていますね。
髙橋:最近よく、ロビー企業やコンサルティング企業が、官庁の幹部や政治家に直接働きかけて規制に介入したり、無理に分析レポートの業務を受注したりすることに対して、特に若手の職員がフラストレーションを感じているという話を耳にします。
トップダウンで降って湧いたように生じる業務に、本来のありかたとしてそれでいいのか、という思いがあるんでしょうね。もちろん、それがちょうど役所のニーズに合っていて採用されるということもありますが。
井上:髙橋さんのところにもそういう相談があるんですか。
髙橋:たまにありますが、私は相談された時点で一旦止めます。民間企業で考えても、いきなり取引先の営業が自社の偉い人に電話をかけて、一方的に話を進めようとしたら、現場の人は絶対いい気持ちにならないですよね?それは官庁でも同じですよ、その辺の段取りは大丈夫ですか?、と。そう説明すると、たいてい我に返って考え直してくれます(笑)。
井上:なぜそういうことが起こるのでしょうか。
髙橋:先ほど営業の視野狭窄の話をしましたが、同じようなことかと思います。例えば入札額を聞いてくれ、みたいな話は、多分全く悪気がなくて、民間企業同士では、ある程度水面下で金額も含めてすり合わせて物事を進めていくスタイルも商慣習としてはあるわけで、その感覚で考えているのかもしれないですね。実際、偉い人に話を通さないと全く話が通らないこともあるので、まずは偉い人に・・というのも気持ちとしてはわかります。ただ、気持ち先行で突っ込んでしまい、ステークホルダーの関係性とか、順番とかを考えないとマイナスに働くことがあります。
井上:企業側でも段取りの理解が必要ということですね。
髙橋:昭和の頃はそういうのも普通だったと言いますよね。田中角栄などは有名な話ですが、自宅に行列ができて、一人ずつ話を聞いていって、田中角栄が役所に電話をしたらその場で規制が変わるなんていうのも日常茶飯事だったわけで。今はそういう昭和の陳情スタイルも変わってきていると感じます。
米国や英国では、いきすぎたロビー活動に歯止めをかけるために、規制が設けられました。登録制にして活動できる人が限られるようになり、ロビー企業側でも自主的な倫理的な規定(倫理コード)を定めていたりします。日本でもそうなる可能性は十分にあり、そうなれば昭和の陳情スタイルは消滅するかもしれません。
井上:大きな転換についていけるのか、昭和のまま乗り遅れてしまうのか、企業にとっても問われるべき時なんですね。

パブリックリレーションズで培った社会視点はパブリックアフェアーズに活かせる武器である
井上:我々オズマのパブリックアフェアーズチームが髙橋さんと協業させていただくにあたっては、相互の強みで補完しあえるところが本当にありがたいところで。特に髙橋さんがお持ちの“目利き力”、ここはなかなか、我々民間企業が学んで習得できるものではありません。そこは髙橋さんがいてこそ、よりクライアントに対して高い価値を提供して貢献できる部分です。
髙橋:ありがとうございます。私が得意としているのは個々の政策そのものに詳しいというよりも、交渉の段取りをアドバイスしたり交通整理ができるといったところで。テーマを問わず幅広く対応できるのは自分自身で強みだと捉えています。
私のほうがオズマと一緒に取り組みをさせてもらっている中で、自分にはないなと感じるのはやはりPRの視点です。社会の流れを捉えて世論に訴える視点を持てるPR会社が行うパブリックアフェアーズ活動は、アメリカではむしろ主流ですが、日本ではまだ少ないと思います。PAだけ、とか、PRだけになっちゃうんですよね。社会への発信という視点も入れてもらいながら、パブリックアフェアーズの設計から協業できるのは非常に心強いですね。
パブリックアフェアーズとパブリックリレーションズが両輪となって企業の活動を支えていけるのが良い形だと思います。
井上:変化のスピードが著しく加速しているこの時代、企業も既存の事業を継続するだけでなく、新しい事業展開をそう遠くない将来に考えなければならない場面にも直面します。そのうえでは、ルール形成にもアクティブに取り組んでいく姿勢が必要で、乗り遅れれば自社の事業が衰退していくことにもなりかねません。
髙橋:公共の利益を考えるという話をすると、自社だけでなく競合にも利益がもたらされるのは許容できない、と二の足を踏んでしまう企業も存在します。でも、競合も含めてみんなで新しい市場を創っていくんだという感覚で、勇気をもって動くことが大事だと私は思います。市場が小さいまま争うより、市場自体を広げてから争う方が、得ですよね。
井上:社会の潮流に適切に乗ることができれば、マーケットの拡大も期待できますし、自社のレピュテーション向上にもつながりますよね。企業に対して価値の転換を促すことも、あいだに入る私たちがもっと推し進めていくべきことであると改めて思いました。
髙橋さんとは今後も、ヘルスケアはもちろん幅広い領域で、パブリックアフェアーズの視点とパブリックリレーションズの視点、双方の強みで補完しながら業務に臨んでいきたいと思います。今日はありがとうございました。


元厚生労働官僚(国家一種(法律職))。新型インフルエンザや東日本大震災の対策など、危機管理における省内統括部門を中心に勤務。課長補佐で退職後、グラスゴー大学(英国)で国際安全保障学(社会・文化論)修士号取得。参議院議員秘書、エジンバラ大学博士課程(中途退学)、博報堂(常駐)などを経て、公共政策コンサルタントとして活動。参議院議員事務所(当時)では議員秘書として、与党の政策提言書や議員立法のドラフト作成に従事し、質疑調整、議員の原稿・講演資料作成などを担当。

パブリック・アフェアーズチーム
国際NGOにて、アドボカシー活動のプロボノ経験あり。メディアの編集委員・編集長クラスに加え、NGPOといったソーシャルセクターや政治家・官僚といったポリシーセクターに広くネットワークを持ち、パブリックアフェアーズ、アドボカシーが専門分野。社会課題と企業・団体の課題を掛け合わせた「ルール形成戦略」キャンペーンの立案・実施を得意とする。観光、製薬、ITなど幅広い分野の公共政策キャンペーンでプロジェクトリーダーを務める。
◇ 多摩大学ルール形成戦略研究所客員研究員
◇ 経済安全保障コーディネーター
同じカテゴリーのコラム
-
不祥事発覚による生活者意識への影響は一括りにあらず ~企業不祥事に関する生活者への意識調査の結果概要~
- #ウズ研
- #危機管理広報

-
PAリレー対談~ルール形成の現場から(7)政治家と民間が共に取り組む変革とは【後編】 福田峰之さん(多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授/株式会社H2&DX社会研究所代表)
- #ウズ研
- #ルール形成コミュニケーション
.png)